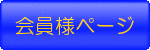航空大学校、航空保安大学校
独立行政法人 航空大学校
日本の民間航空は、昭和27年に再開されることになりましたが、終戦後7年の空白期間に航空機の性能は飛躍的に
向上し、航空保安施設も近代化が進んでいました。この為、航空従事者には高度な技術と知識が要求されるようになり、
一刻も早く、新しい技術を習得した要員の育成が待たれるようになりました。このような情勢から、航空機操縦士の養成を
国が実施することとなり、昭和29年7月、運輸省の附属機関として、航空大学校が宮崎市に設立され、同年10月開校され
ました。
航空大学校における養成内容は、航空機操縦士の基礎教育を行うもので、その課程は、計画的新人養成を目的とする
本科と、経験者を対象とする専修科となっていましたが、この専修科は、経験者という制約があった為、昭和33年3月で
廃止になりました。
本科の養成規模は、入学資格を短大卒とする当初の10名から昭和33年度に30名に、昭和43年度からは入学資格を
高校卒とする90名、さらに昭和46年度には135名と逐次拡大されましたが、これに伴ない飛行訓練空域等が宮崎1ケ所
では不足することになった為、昭和44年度には仙台分校、昭和47年度には帯広分校が開校されました。
昭和49年度後半以降、社会経済情勢の著しい変動により、航空大学校の養成規模は、昭和51年度入学生から108名
に減員され、その後、昭和53年度からは本科98名となったほか、小型機産業航空界の発展等に伴い養成人員10名の
回転翼操縦士基礎教育を行う別科が新設されました。別科の回転翼操縦士に係る飛行訓練については、防衛庁に委託
する形で行われることになりました。
昭和62年度から、第4世代航空機の出現等、航空機に係る最近の目覚ましい技術革新、運航環境の変化等に伴い、
入学資格を大学2年修了以上(同等以上を含む)とするとともに、航空電子等の航空技術に関する専門教育の充実を
図ることになりました。
また、仙台課程における訓練機として、双発ターボプロップ機ビーチクラフト式C90A型機が導入されました。
平成元年度から、それまで防衛庁に委託されて来た別科の回転翼飛行訓練をヒューズ式 269C型導入の上、新たに
航空大学校に於いて実施することになりました。
平成4年度から、宮崎課程の訓練機として、ビーチクラフト式A-36型機を導入、また平成6年度には帯広課程の訓練
機も同機種に更新し単発機課程の訓練機種が統一されました。
平成5年7月12日、「本科」及び「別科」の名称は、それぞれ「飛行機操縦科」及び「回転翼航空機操縦科」となった。
平成6年度にスピン訓練機として、スリングスビー式T67M・MK II 型機が宮崎課程に導入されましたが、平成7年度に
同機材を帯広課程のスピン体験機となりました。
平成10年度学生募集をもって、回転翼航空機操縦科学生の募集が中止されました。
平成14年度からは、パイロットとしての資質を持った数多くの応募者を受け入れるため専修学校の専門課程を修了し、
専門士の称号を付与された者を入学資格に加えられました。なお、平成13年4月に航空大学校は、国の直接運営から
離れ、「独立行政法人航空大学校」として、修業期間を2年4ヶ月から2年に短縮されました。
航空大学校に入るには
専門学校修了者に対する専門士の称号を付与された者
-4.5~+2.0ジオプトリー以内であること。
試験に進む(試験地:東京10月に行われる)。さらに約50名前後が3次試験に進む。
(試験地・宮崎/1月中旬に行われる)。最終的には36名を上限として採用される。最終合格者の発表は2月末。